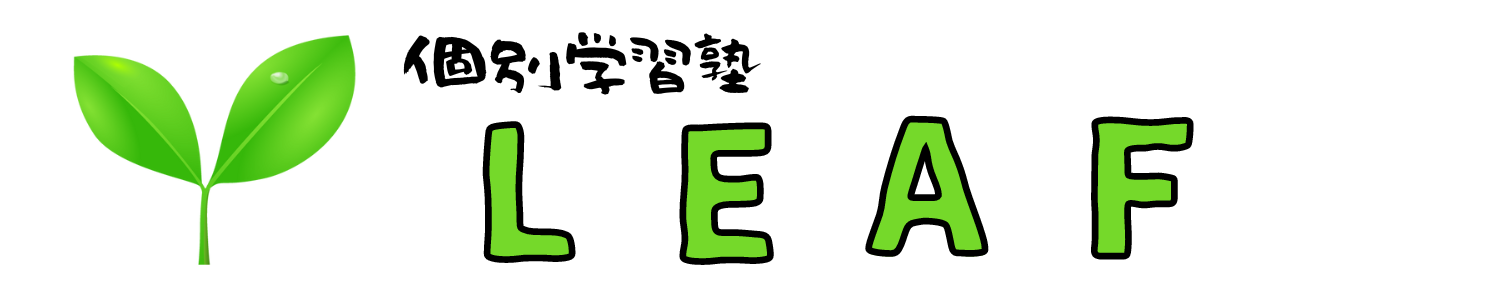「校長先生」は二重言葉?違和感なく使っている言葉[#79]
「校長先生」って、実は“二重言葉”なんだそうです。
「校長」という言葉自体に「先生」という意味が含まれているので、
本来なら「○○校長」と言うのが正しい形です。
でも、普段の会話では「校長先生」と言っても違和感はまったくありませんよね。
たとえば、朝礼で「校長先生のお話です」と言われても、誰も変だとは思わないはずです。
これは、言葉が“ていねい”になった結果、二重になってしまったという現象です。
つまり、意味がかぶっていても、「より敬意を表したい」という気持ちから生まれた自然な表現なんですね。
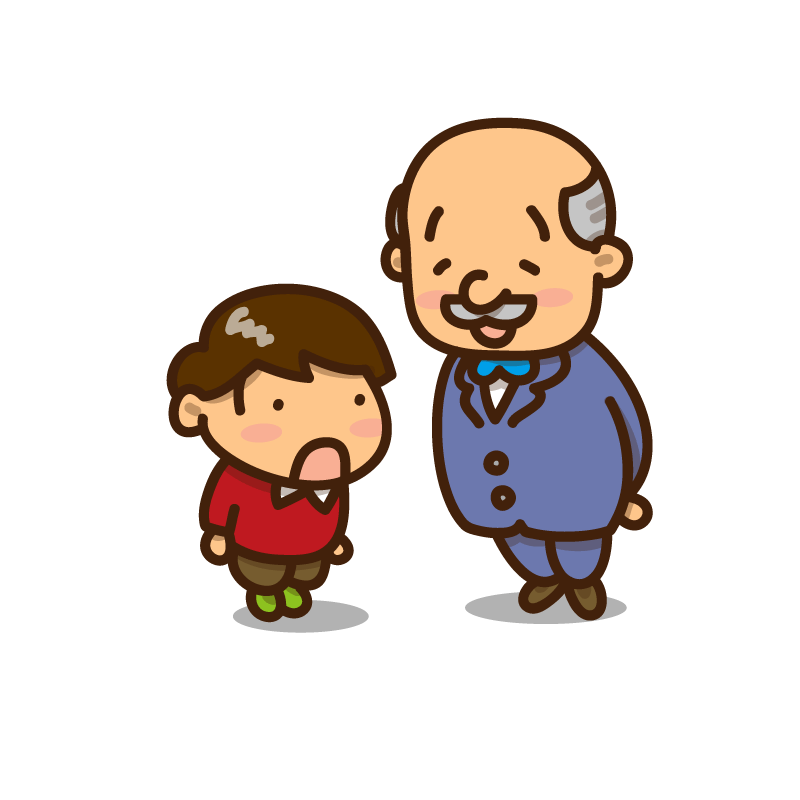
「サハラ砂漠」は「砂漠砂漠」!?
中学1年生の地理で「サハラ砂漠」を習った人も多いでしょう。
実はこの「サハラ」もアラビア語で「砂漠」という意味です。
だから「サハラ砂漠」は、文字通り「砂漠砂漠」と言っていることになります。
同じような例では「ゴビ砂漠」もあります。
モンゴル語で「ゴビ」は“乾いた土地・砂漠”という意味なので、こちらも「砂漠砂漠」。
なんだか不思議ですね。
でも、こういう言い方をする理由もちゃんとあります。
「サハラ」や「ゴビ」だけでは日本人には“何のことか”が伝わりにくいからです。
「砂漠」という日本語をつけることで、「あ、地名じゃなくて“砂漠の名前”なんだ」とわかりやすくなるんです。
つまり、外国語の固有名詞を日本語でわかりやすくするための“補足”として重ねているというわけです。
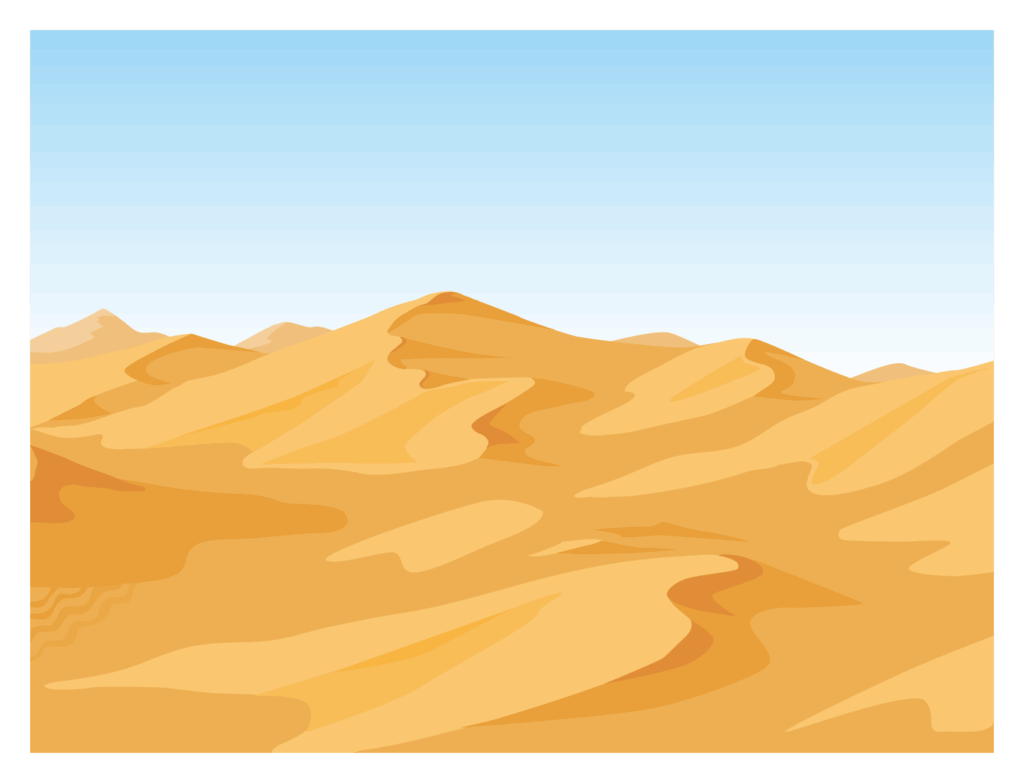
「マグカップ」も「カップカップ」
日常生活の中にも、意外と二重言葉があります。
たとえば「マグカップ」。
英語の「mug」は「取っ手のついたカップ」のこと。
つまり、「マグカップ」は「カップカップ」。
同じように、「クーポン券」も「クーポン=券」、「チゲ鍋」も「チゲ=鍋」。
(↓ChatGPT情報によると)
ついでに言うと、「ATMマシン」(=自動預け払い機マシン)も英語圏では実際に使われる二重言葉です。
人間って、「わかりやすく」「強調したくて」言葉を重ねてしまうんですね。
「荒川川」になる?英語の不思議
道路標識や地図などで見かける「Arakawa River」も面白い例です。
直訳すると「荒川川」。
日本人からすると「ちょっと変じゃない?」と思ってしまいます。
でも、英語では「Arakawa River」と書いたほうがわかりやすいんです。
もし「Ara River」と言われても、日本人にはどこの川かわかりにくいよね。
「Arakawa River」とすることで、外国人にも日本の地名として伝わりやすく、日本人にも理解しやすい形になるのです。
一方、「富士山」は「Mt. Fuji」。
「Fuji Mountain」とは言いません。
これは「Fuji」が地名ではなく、山の固有名として世界的に知られているからです。
言語は、使う人の文化や認識の仕方によってルールが変わるという良い例ですね。
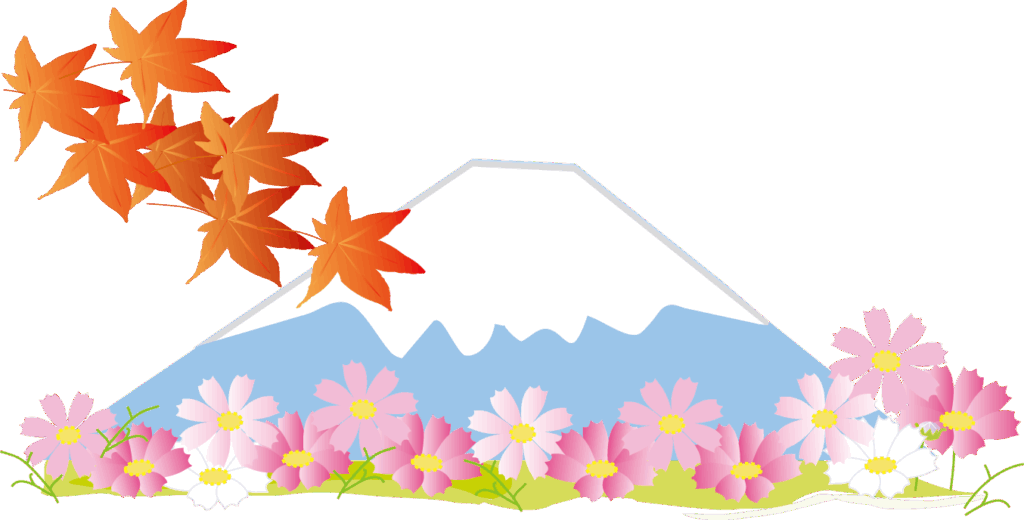
二重言葉が生まれる理由
こうして見ると、二重言葉には大きく3つのパターンがあるようです。
- ていねいに言いたくて重ねる(例:「校長先生」)
- 外国語を日本語で補足してわかりやすくする(例:「サハラ砂漠」「Arakawa River」)
- 日本語にしたときに意味の重なりに気づかず使っている(例:「マグカップ」「チゲ鍋」)
どれも、「おかしい」と言うよりは、「自然な進化の結果」なんですね。
ことばは生きている
言葉って、教科書に書かれた通りのルールだけで動いているわけではありません。
人が使いやすいように、わかりやすいように、少しずつ形を変えていきます。
だから、「校長先生」も「サハラ砂漠」も、間違いではなく、
人が心地よく使えるように変化した“生きた言葉”なんです。
ちょっとした違和感の中に、言葉の面白さが隠れていますね。
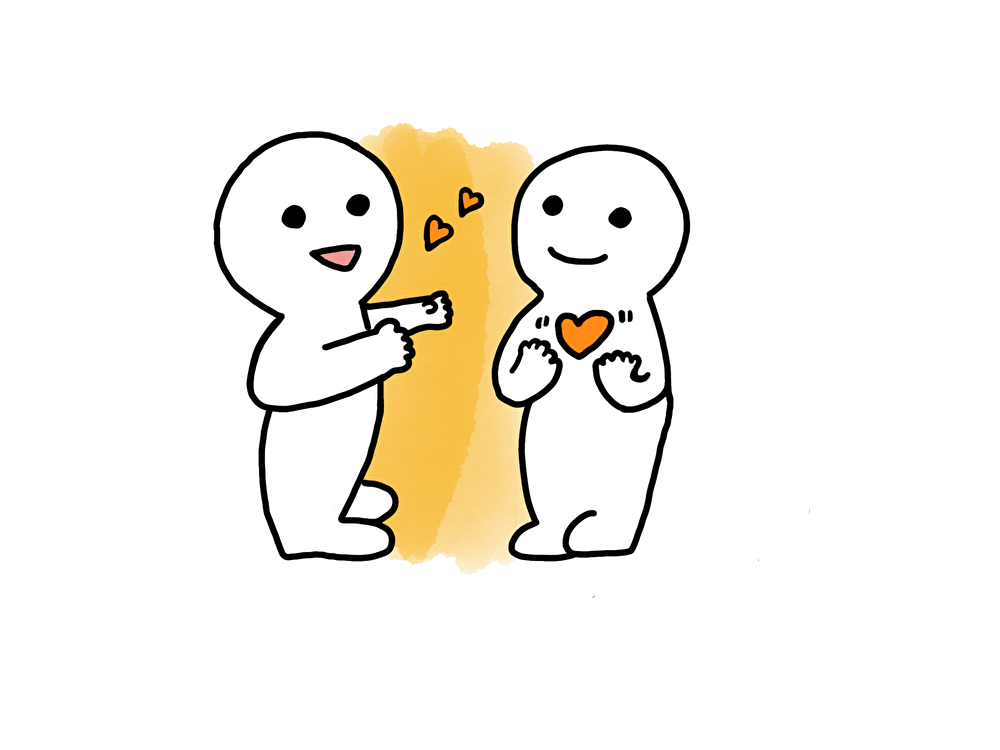
【LEAFの体験授業・お問合せは】
・体験授業・ご入会・ご退会
・お問い合せ
【学力支援ページもご覧ください】
・【脳葉強化 ~ひらめきラボ~】 脳細胞フル回転!問題解決への挑戦!
・ 頑張る子のために~反復プリント~【ダウンロードページ】
【引用・利用サイト】