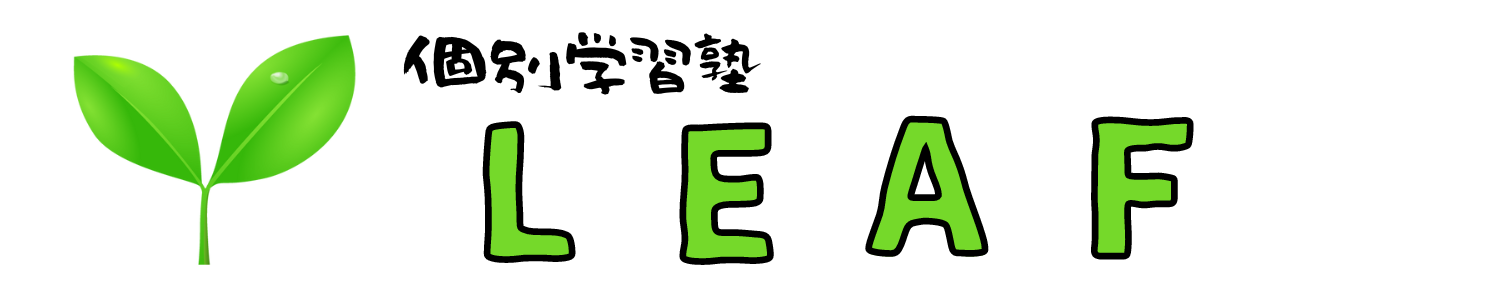第2回教達検(25.11.13)に向けて:残り2週間でできること(第1回教達検の平均点予測)[#77]
年によって多少異なりますが、近隣の高校の志望校合格ライン(教達検結果)は以下のようになります。
吉田高校(理数科)425点以上
吉田高校(普通科)375点以上
富士河口湖高校(普通科)300点以上
富士北稜高校(総合学科)250点以上
※合格ラインは、年次によって変わってきます。
※上記の点数は合格ライン(平均・中央値のやや下)の得点です。最低点数は年次よって変わります。
学校や塾によって、多少誤差はあると思いますが、おおむね上記のような点数になると思われます。
2025年の第1回教達検は、若干やさしめだったようで、得点はやや高めの結果となったようです。
上記の得点にプラス10点~15点くらいするとよいかもしれません。
2025年第1回だけに絞ると得点の目安は以下のようになると考えています。
吉田高校(理数科)440点以上
吉田高校(普通科)385点以上
富士河口湖高校(普通科)310点以上
富士北稜高校(総合学科)250点以上
準備をしてきた子たちにとってみると頑張った成果が出やすい難易度テストでしたね。
基本問題や解答のしやすい問題が多かったように感じます。
逆に、準備が不十分だった子は、普段の到達度テストなどの得点と変わらず、他の生徒と比べると大きく得点差が開いてしまったのではないでしょうか。
進路指導・相談で参考にされるテストですので、この差は大きく影響しそうですよね。
ただ、得点だけ見て安易に進路の決定・判断するのも危ういかもしれません。
今回のように、テスト難易度がやさしいとき、得点の差が「実力による差」なのか「準備の違いによる差」なのかが見分けにくいからです。
第2回教達検が例年通りの難易度に戻った際に、得点を大きく下げてしまう生徒がいます。
こうした生徒は、第1回教達検の前に基本問題を繰り返し解いて知識を増やしていたり、過去問演習によって傾向をつかんでいたりすることで、たまたま類題が出題され高得点を取れたケースが考えられます。
つまり、学力が大きく伸びたというよりは、「テストの問題に対応できただけの表面的な力」がついた状態です。
もっとも、これはこれで素晴らしいことです。努力を重ねた結果であり、継続していけば本当の学力・実力がついていく可能性は高いでしょう。
ただし現時点では、基礎的な実力が十分でないため、テストの難易度によって得点が大きくぶれてしまう傾向があります。
一方で、今回、準備が不十分で志望校に対して低得点となってしまった生徒の中には、適切かつ十分な準備ができていれば、高得点を取れていた可能性がある子もいると思います。
もちろん、今回準備が不足していたことは反省すべき点ですが、今回の結果だけをもとに進路を早々に決定・判断してしまうのは、少し考え直したほうがよいかもしれません。
高校の進学先によって、その後の進路や将来の選択肢は大きく変わります。目先の高校合格・不合格だけにとらわれず、もう少し先を見据えて高校を選ぶことが大切です。その方がきっと、高校3年間の生活もより充実したものになるでしょう。
中学3年生にはいつも伝えていますが、「行ける高校より、行きたい高校を目標に」です。
「そうはいっても、得点的に行きたい高校には届いていないから…」と思うかもしれません。
しかし、10月や11月の時点でその判断をしてしまうのは、あまりにも早すぎます。ましてや第2回教達検の前であれば、なおさらです。
「適切・適量の準備ができておらず、自分の力を発揮できていない状態で、本当に判断してしまっていいのか?」
「本当に後悔しない行動ができているのか?」
――今一度、そう問いかけてみてほしいと思います。
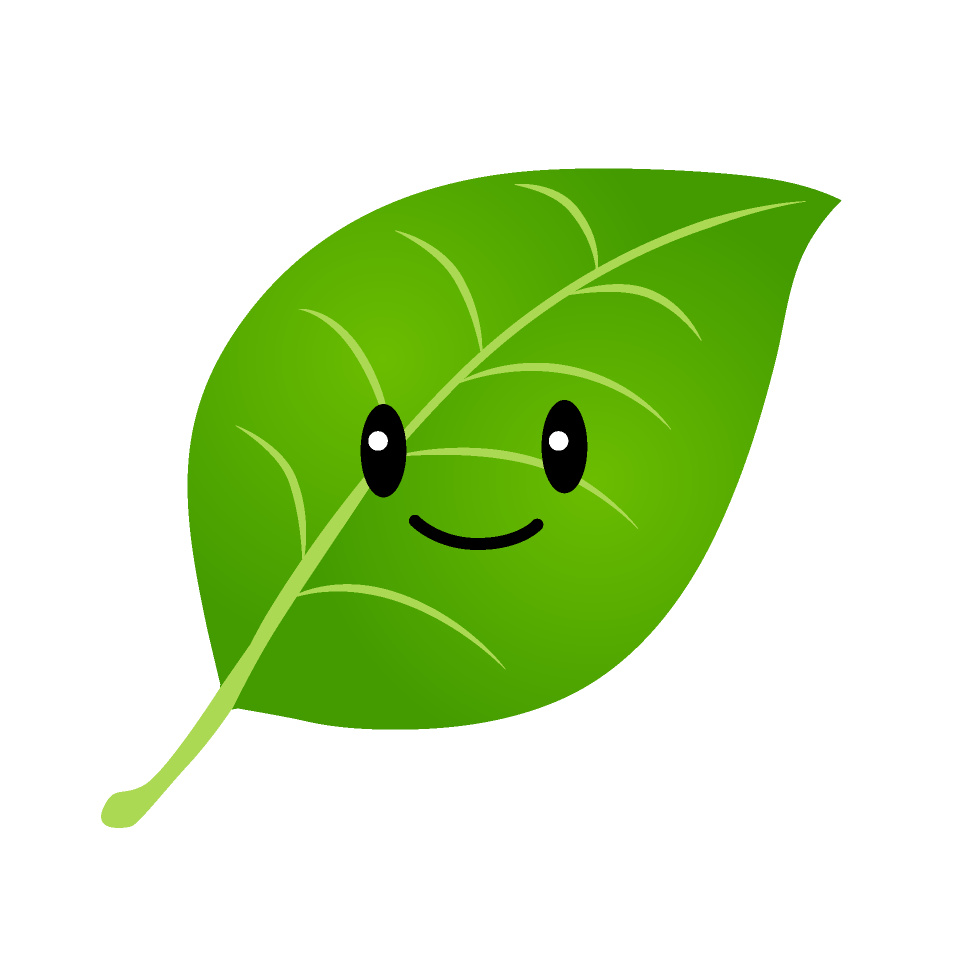
勉強が好きな子もいますが、多くの子は「やらされて」勉強しています。
でも、そんな子たちが“将来を見据えて”勉強し始めたときの成長は、本当に驚くほどです。
塾の先生って、本来そういう“きっかけ”を与える存在だと思うんです。(が、残念ながらそのきっかけを与えられる先生が少なくて・・・)
そのきっかけは、子ども一人ひとり違います。だからこそ、目の前の生徒に合った話や気づきを与えなければ、子どもは変わりません。もしかしたら、そのきっかけを一番与えられるのは、子どもを一番近くで見ている“保護者の方”かもしれません。でも、子どもは思春期。素直に話を聞いてくれる子ばかりではないですよね。
だからこそ、塾の先生がきっかけを与えることが大切だと感じています。目の前の生徒をしっかり理解して、その子に合った言葉や気づきを伝えられるかどうか――それが、その先生次第なんです。
今回の記事は、勉強の仕方にフォーカスした内容です。
第2回教達検に向け、どういった気持ちで取り組んできたかは、以下の記事をご参照ください。↓↓↓↓↓
第1回教達検が終わり進路指導へ 第2回教達検・入試で得点を上げた生徒はこんな生徒だった[#24]
1年前に書いた記事なのですが、読み直してみると、よいこと書いたなーと自分でも感じてしまいました。(〃´∪`〃)ゞ
第2回教達検まで残り2週間!~やっておきたいこと~
ここでの”やっておきたいこと”は、「実力を上げるため」というより「テストでどう点数を上げるか」に近い内容です。
本当の実力をつけるためには、やはり日々の積み重ねが大切です。
今回の記事で紹介する内容は、その日々の学習への“きっかけ”になればと思い、まとめました。
テストが終わったあとに「(勉強)お~わり!」で終わってしまわないことを願っています。
[ ページTOPへ ]
第2回教達検に向けて
- 第1回教達検のテスト範囲増えた内容は100%に近い確率で出題されます。
理科なら「イオン」「生殖」、数学なら「2次方程式」「2次関数」、英語なら「関係代名詞(名詞的用法)」、社会は「公民分野」など - 第1回で出た単元は出題されにくいので、その他の範囲を優先(主に理科)
たとえば理科で「天気」の単元のうち、第1回で「前線」が出題されたなら、第2回前は「湿度」の勉強をするなど。
※1回目でも2回目でも出題されたことはありますが、連続で出題される可能性はかなり低いです。 - 過去問が手に入るなら、過去問演習は必須です!
※第2回教達検の過去問だけではなく、第1回教達検の過去問のうち、今年の第1回に出題されなかった問題をやっておくのもお勧めです。

小手先の勉強法に近いので、正直あまりおすすめはしません。
むしろ、この方法はできれば“やってほしくない”です。
この小手先の勉強をするよりも、前もってしっかり準備して、実力をつけてほしい!
それが本心です。
教科別の勉強法の詳細はありますが、トピックのみ載せますね。
*英語の長文の時間配分や英作文の対策
*国語の漢字でやっておくべき語
*理科の計算問題は第1回・第2回で出題傾向が決まる
*数学の統計(代表値や相対度数・箱ひげ図)の出題傾向
中2の冬から始める教達検・入試対策するなら・・・
*英語の長文読解を解けるようになるために、すべきこと
*数学は大問1・2を完璧になるために
*社会の歴史は流れをつかむことが重要!→まずすべきこと
*社会の地理・理科は学習済みの単元は教達検レベルの勉強をスタート
中2の冬には、基本知識の定着をなど教達検・入試に向けて動き始めた方がよい時期です。
中3の夏ごろには教達検・入試レベルの問題を本格的に対策していくと、ゆるぎない実力が身についていきます。
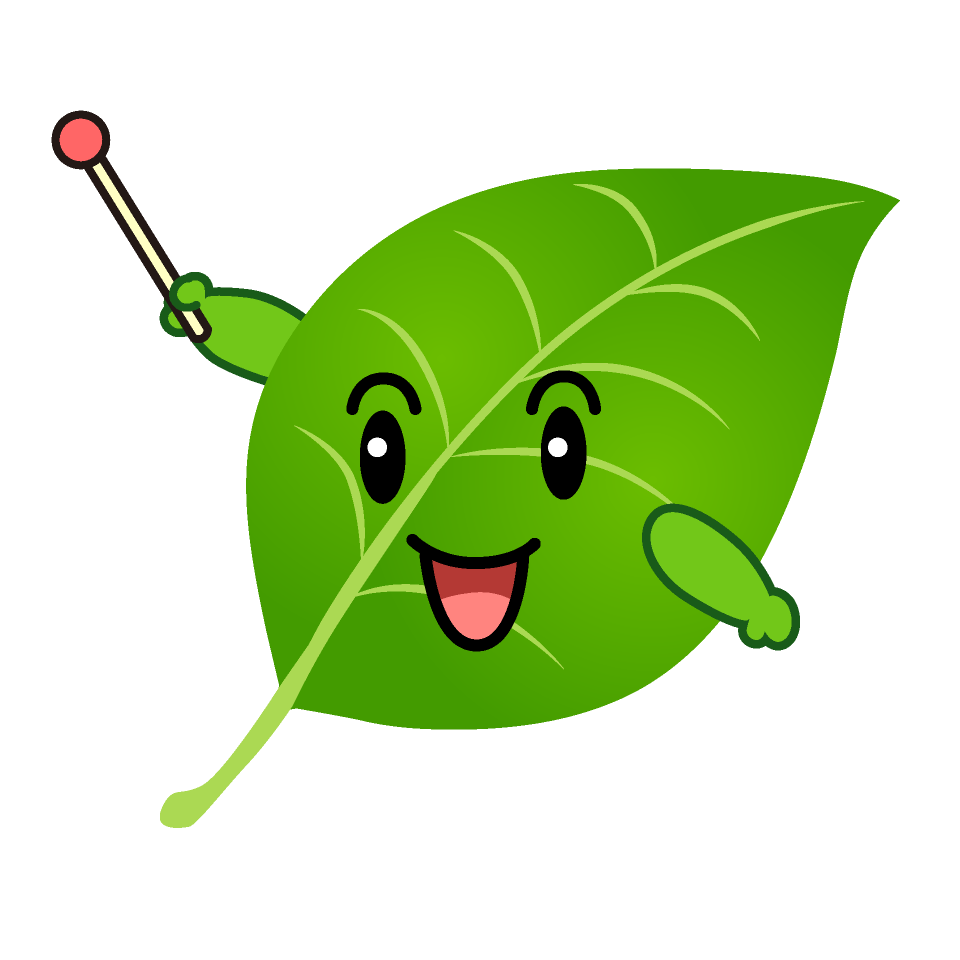
[ ページTOPへ ]
【LEAFの体験授業・お問合せは】
・体験授業・ご入会・ご退会
・お問い合せ
【学力支援ページもご覧ください】
・【脳葉強化 ~ひらめきラボ~】 脳細胞フル回転!問題解決への挑戦!
・ 頑張る子のために~反復プリント~【ダウンロードページ】