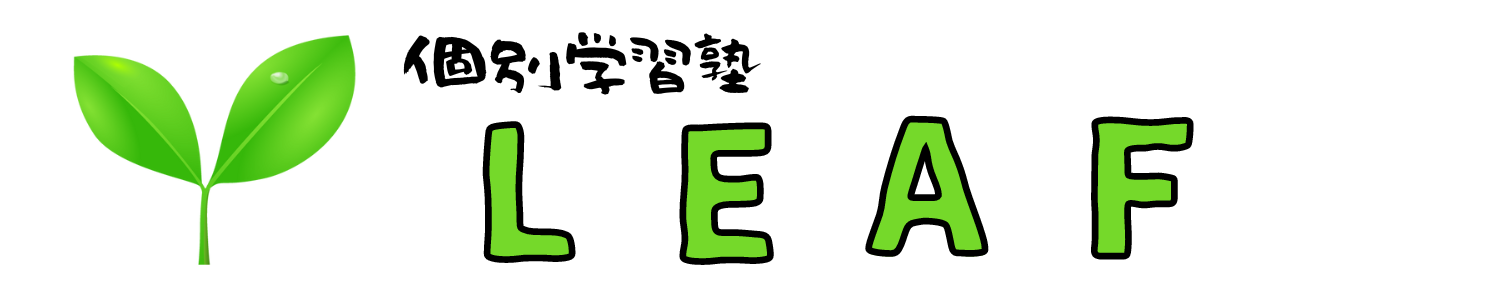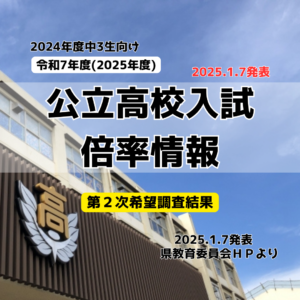【脳葉強化】『双子問題 バイバイ♪』 ひらめきラボ《0014》 ~多く経験を積むと常識が増えるが思考が停止になる人も~
解答:
レベル1:ヤマトとタケル
レベル2:59分
レベル3:三つ子(以上)だったから双子ではない
解説:
レベル1の解説
瞬時に気が付けるのは、本人同士ですね。自分がヤマトなら、もう一人はタケルですからね。
レベル2の解説
バイバイ菌を1つ入れたときと、2つ入れたときで短縮される時間は1分です。
1つ入れたときは1時間(60分)ですので、2つ入れたときは1分短縮だれた59分です。
よくあるミスは30分って考えてしまうようです。
(もう少し詳しく)
バイバイ菌を1つ入れたとき、1→2→4→8→16→32→64→128・・・のように増えますよね。
バイバイ菌を2つ入れたとき、2→4→8→16→32→64→128・・・のように増えますよね。
容器の大きさはわかりませんが、例えば、バイバイ菌が128個になったら、容器いっぱいになったとしたら、
バイバイ菌を1つ入れたときと、2つ入れたときで、短縮される時間は、最初の1→2になる1分だけです。
レベル3の解説
「兄弟」ではなく「双子ではない」というところがポイントですね。
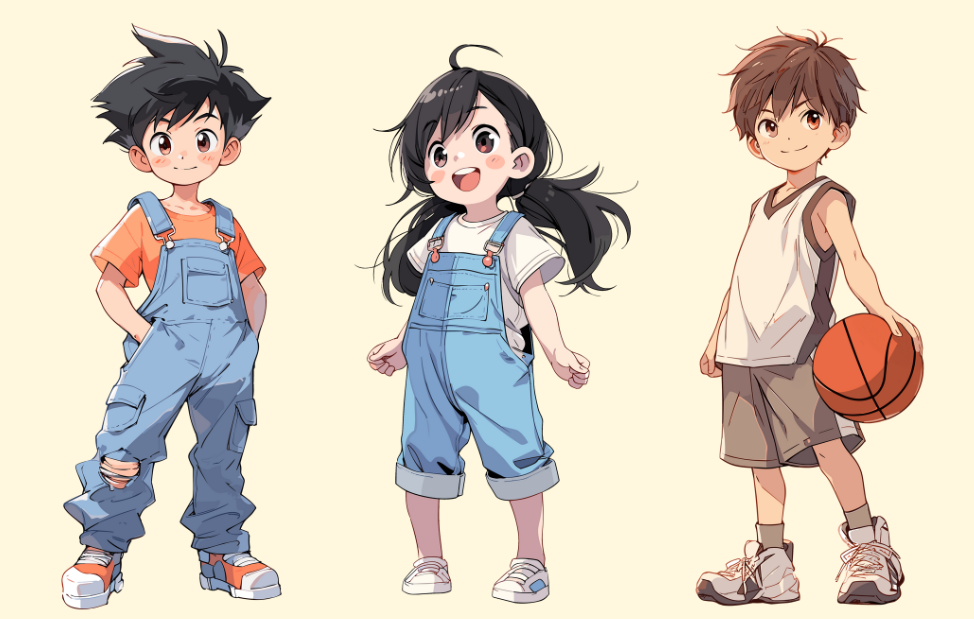

いかがでしたか。状況をイメージすることができた人は、瞬時に分かったのではないでしょうか。
三つ子の問題は、知り合いにいたらすぐに気が付けるでしょうが、いなかったら考えがそこまで及ばないかもしれません。
経験があることには、考えが及びやすいですが、未経験のことまで考えを及ぶことは難しいかもしれません。
だから、義務教育では、いろいろなことを学ぶ機会が与えられているのだと思います。
知識を得るだけでは、いざという時に考えが及ばないことがあり、実体験したことはより記憶が強化されているのでしょうね。
経験を積むことはやはり大切ですね。
しかし、一方で、経験則に頼り切っていると、思考が停止してしまうこともあります。そんな内容を書き加えておきますね。
多く経験を積むと常識が増えるが思考が停止になる人も
私たちは日々、様々な経験を重ねながら成長していきます。しかし、その過程で思考の柔軟性を失ってしまうことがあります。今回は、経験を積むことで起こりうる「思考停止」という現象について考えてみましょう。
子供の学習過程から見える課題
例えば、算数の問題を解く子供たちを見てみましょう。最初は一つ一つ丁寧に考えながら解いていた問題も、練習を重ねるうちに「このパターンならこう解けばいい」という形式的な解き方を身につけていきます。
これは一見、効率的な学習方法に思えます。しかし、テストで似て非なる問題に出会ったとき、条件をしっかり読まずにパターン化した解き方を当てはめてしまい、ミスをしてしまうことがあります。
大人の世界でも起こる同じ現象
この現象は、実は私たち大人の世界でも頻繁に見られます。特に仕事の場面では顕著です。
ある方法で成功を収めると、人はその方法を「正解」として認識します。そして、新しい課題に直面したときも、つい過去の成功体験をそのまま当てはめようとしてしまいます。しかし、ビジネスの現場は日々変化しており、昨日の正解が今日の正解とは限りません。
経験が足かせになるとき
経験を積めば積むほど、私たちは「これまでこうやってきたから」という思考に陥りやすくなります。その結果:
- 新しいアイデアを受け入れにくくなる
- 状況の変化に気づきにくくなる
- 臨機応変な対応が苦手になる
- 問題の本質を見失いがちになる
思考停止を防ぐために
では、どうすれば経験を活かしながらも、思考停止に陥らない人になれるのでしょうか?
- 常に「なぜ?」を持ち続ける
当たり前だと思っていることにも、時々疑問を投げかけてみましょう。 - 新しい視点を意識的に取り入れる
若手の意見を聞いたり、異なる分野の知識を学んだりすることで、固定観念を揺さぶることができます。 - 失敗を恐れない姿勢を持つ
たとえ経験があっても、新しいやり方にチャレンジする勇気を持ちましょう。 - 状況を丁寧に観察する習慣をつける
似ているように見える状況でも、細かな違いに目を向ける習慣をつけることが大切です。
経験を積むことは確かに大切です。しかし、それと同じくらい重要なのは、常に学ぶ姿勢を持ち続けることです。経験を「引き出し」として持ちながらも、その引き出しに縛られることなく、柔軟な思考を維持できる人こそが、真の意味で成長し続けることができるのではないでしょうか。