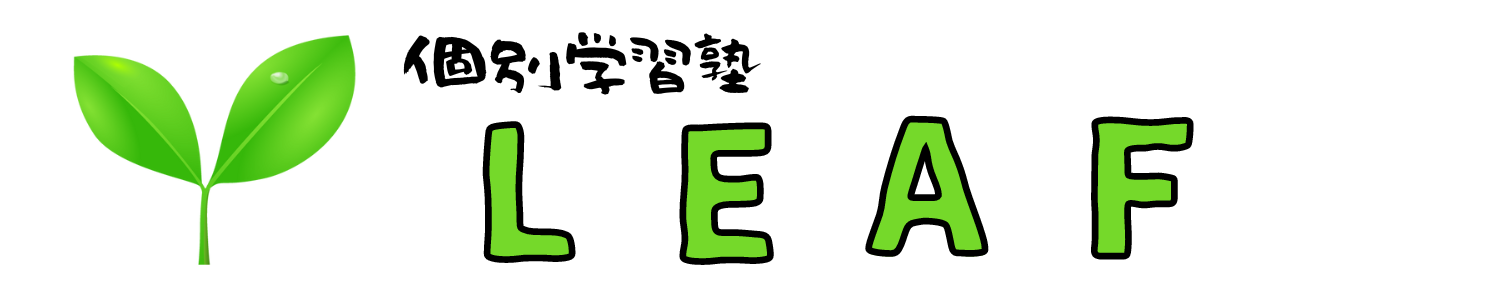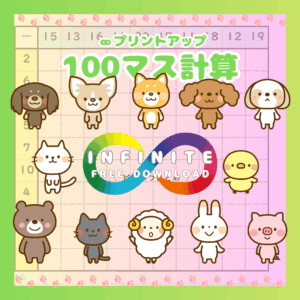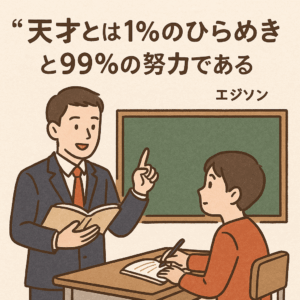【脳葉強化】『油分け算② 10L・3Lをつくる』 ひらめきラボ《0030》 ~子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできること~
解答:
下の表を参照
解説: レベル1
7Lのマスと4Lのマスを使って、10Lの水を空のおけに測り取る方法は以下の通りです。

- 7Lのマスに満杯に入れる
- 7Lの水のうち4Lのマスに4L移す(7Lのマスには3L残る)
- 7Lのマスに残った3Lを空のおけに入れる
- 7Lのマスに満杯に入れる
- 7Lのマスの水を空のおけに入れる
これで、10Lの水を空のおけに測り取ることができます。
解説: レベル2
5Lのマスと4Lのマスを使って、3Lの水を空のおけに測り取る方法はいくつかあります。
手順ができるだけ少なくする方法を思いつきましたか?

最小の手数は4回だよ
■その1

- 5Lのマスに満杯に入れる
- 5Lの水のうち4Lのマスに4L移す(5Lのマスには1L残る)
- 5Lのマスに残った1Lを空のおけに入れる
- 4Lのマスの水を水の入ったおけに戻す
1~4を繰り返して1Lずつ測ることで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。
■その2

- 4Lのマスに満杯に入れる
- 4Lの水を5Lのマスにすべて移す
- 4Lのマスに満杯に入れる
- 4Lのマスの水を5Lのマスに入れていき、5Lのマスを満杯にする(1Lの水が移動するので4Lのマスには3Lが残る)
- 4Lに残った3Lを空のおけに入れる
これで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。
その1の時より、手順は少なくてすみますね。
■その3

- 4Lのマスに2Lだけ入れる(※下の図を参照)
- 5Lのマスに満杯に入れる
- 5Lのマスのうち、4Lのマスに2L移す
- 5Lのマスに残った3Lを空のおけに入れる
これで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。
その2よりさらに手順は少なくてすみますね。
★4Lのマスで2Lを測る方法★
下の図のようにマスを傾けると、マスの容量の半分の量を測ることができます。
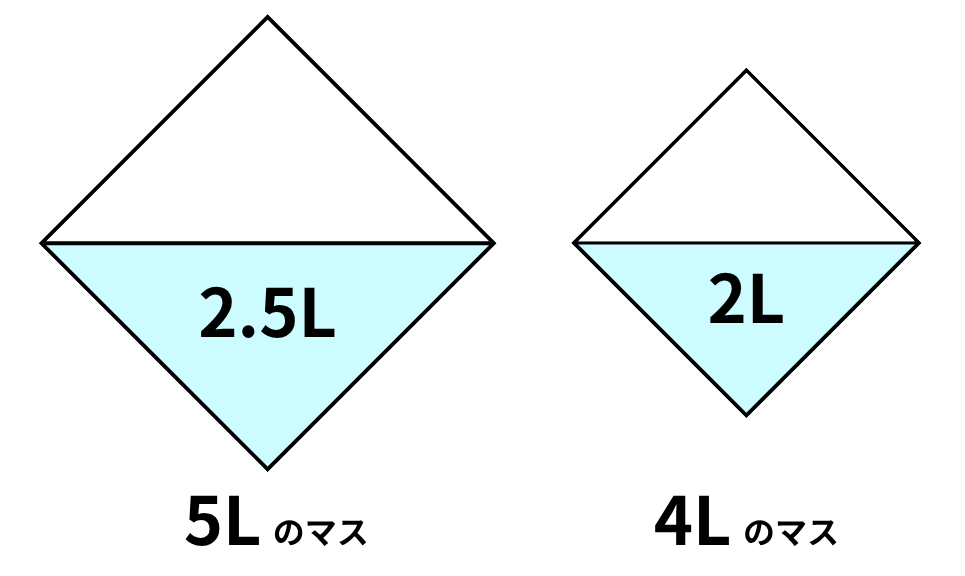
油分け算①はこちらから
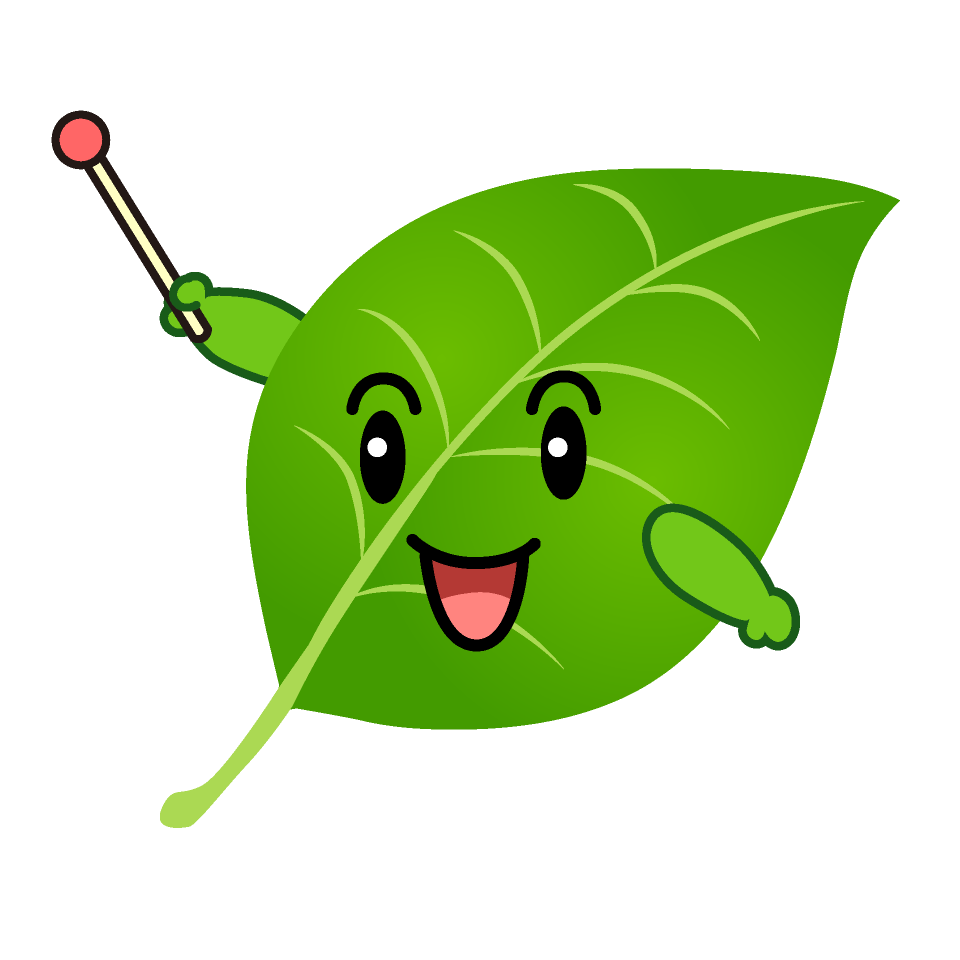
いかがでしたか。
少し工夫すれば、少ない手数で目的を達成できますね。
思考力を鍛えておくことは大切ですね♪
「なんでだろう?」が育てる力
子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできること
子どもに「もっと考えてほしい」「すぐに答えを求めずに、自分で考える力をつけてほしい」と感じたことはありませんか?
考える力は、一生ものの武器です。
ただ、それを育てるには、日々の習慣や環境がとても大きく関わってきます。
今回は、子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできるちょっとした工夫をご紹介します。

1. 「問いかけ」をプレゼントする
大人がすぐに答えを教えるのではなく、「どう思う?」「なんでそうなったと思う?」と問いかけてみましょう。
たとえば、夕食で出た野菜を見て
「これってどこで育ててるんだろうね?」
「これって火を通すとなんで甘くなるんだろう?」
そんな日常の会話の中から、子どもは「考えるきっかけ」をもらえます。
ポイント
✔ 答えをすぐに言わない
✔ 一緒に考える姿勢を見せる
✔ 間違っていても否定しない
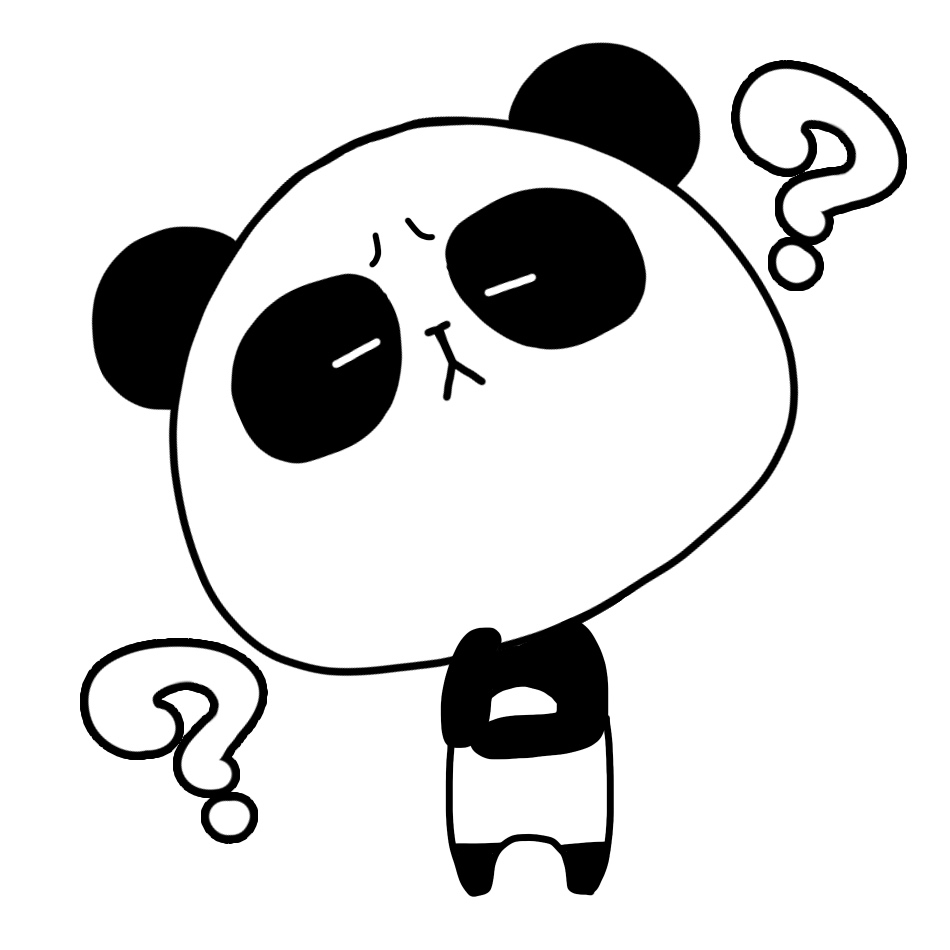
2. 「正解」よりも「過程」に注目する
テストや勉強では、どうしても「正解」に注目しがちです。
でも本当に育てたいのは、「どうやってそこにたどり着いたか」「どんな考え方をしたか」という“過程”。
「どうしてこの答えにしたの?」と理由を聞いてあげましょう。
たとえ答えが違っていても、「よくそこに気づいたね」「考え方は面白いね」と、考えたこと自体を認める声かけが大切です。
3. 「待つ」時間も大事にする
子どもが考えている最中、ついつい手や口を出したくなること、ありますよね。
でも、ここでグッとこらえて“考える時間”を待ってあげることが、とても大切です。
沈黙=理解していない ではありません。
沈黙=頭の中で整理している時間 なのです。
「ゆっくりでいいよ」「じっくり考えてごらん」と安心させてあげる声かけも効果的です。
4. 「遊び」や「会話」からも考える力は育つ
考える力=勉強だけ、ではありません。
ボードゲーム、パズル、なぞなぞ、しりとり……遊びの中にもたくさんの“考える要素”が含まれています。
また、日常会話の中で「もし○○だったら?」「○○と○○、どっちが便利だと思う?」という“たとえ話”や“仮定の話”をするのも、思考力アップに効果的です。
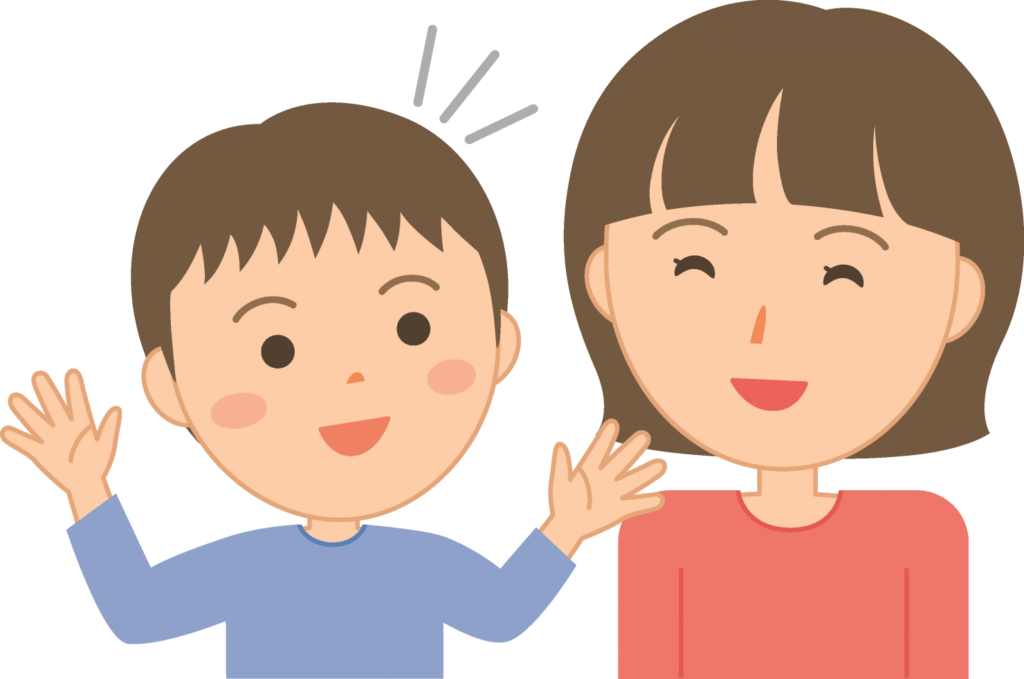
まとめ:考えるクセは、毎日の中にある
考える力は、自然には育ちません。
でも、家庭でのちょっとした声かけや関わり方で、子どもは少しずつ「考えるクセ」を身につけていきます。
大切なのは、「すぐに答えを与えないこと」「一緒に考える時間を楽しむこと」「間違いを恐れない環境をつくること」。
今日の会話の中に、“ひとつだけ問いかけ”を加えてみませんか?
その小さなきっかけが、子どもの思考力を大きく育てていくはずです。