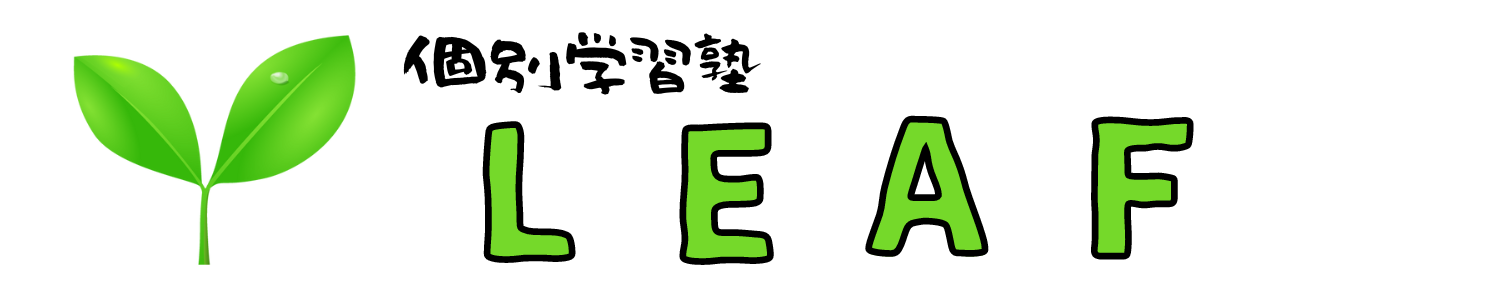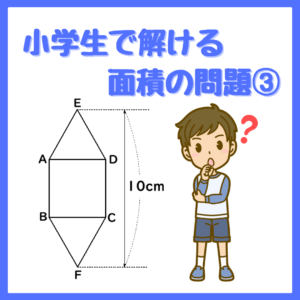ミスしたときの子供の様子でその後の成績がわかる!? ミスから学ぶ – 成績向上への本当の近道[#43]
お子さんは、問題を解いていてミスをすると、すべて消してしまって解きなおしていませんか?
成績が伸び悩む生徒や同じミスを繰り返してしまう生徒の多くに、この「ミスの直し方」という共通の課題があることをご存知でしょうか。
小学校低学年や未就学児を見ていると、とにかく正解したい一心で、ミスをすると「全部なかったことにしたい」という気持ちから、すべてを消して解きなおしをします。「これが違うなら、こっちはどうだろう」と、まるで宝探しのように正解を探そうとするのです。教えている人の表情やまわりの様子を見て判断し、解答を見つけると、とにかくその答えにたどり着きたいという気持ちが先走ってしまいます(これが行き過ぎると、カンニングという危険な道に進んでしまう可能性もあります)。

成長して小学校高学年や中学生になっても、この「ミスしたら全部消して解きなおす」という習慣が抜けない子どもたちがいます。低学年のうちは、それでも大きな問題にはならなかった(または問題に見えなかった)かもしれません。しかし、小学校高学年や中学生になると、これが学習の大きな壁となってしまうことがあるのです。
ミスには様々な種類があります。「ケアレスミス」なのか、「そもそも理解が不十分なことが原因のミス」なのかで、その対処法は大きく異なってきます。算数や数学で言えば、ケアレスミスの中にも、「単純な計算ミス」「公式の使い方ミス」「知識の使い間違い」など、さまざまな種類があるのです。
「ミスをしたら全部消してなかったことにして、もう一度解きなおす」というパターンを続けていると、学習している内容の本質的な理解が深まらないまま進んでしまいます。
典型的な例が、小学生の算数での速さや割合の単元です。これらの単元では、かけ算で求めるときとわり算で求めるときが混在します。わり算でうまくいかないからかけ算に切り替えてしまう子どもたちをよく見かけますが、それまでの単元では、かけ算だけ、わり算だけという単純な計算が中心だったため、複合的な思考が必要になった時に戸惑ってしまうのです。
このような解き方を続けていると、速さや割合の本質的な感覚が身につかないまま進級してしまい、それは算数や数学だけでなく、他の教科の学習にも影響を及ぼしていきます。
理解が不十分なケースは比較的発見しやすいのですが、単純な計算ミスや公式・知識の使い方のミスは見つけにくく、放置すると同じミスを繰り返してしまいがちです。自分の計算ミスの傾向、間違った知識の定着、公式選択のミスなど、「単なるケアレスミス」として軽視してしまう生徒たちは、同じミスを何度も繰り返すことになります。そして、単純な計算ミスが原因なのに、その単元全体が「理解できない」「わからない」という誤った認識を持ってしまう生徒も少なくありません。本来は計算ミスを防ぐ練習をすべきなのに、単元全体の学習を繰り返して時間を無駄にしてしまうケースもあるのです。
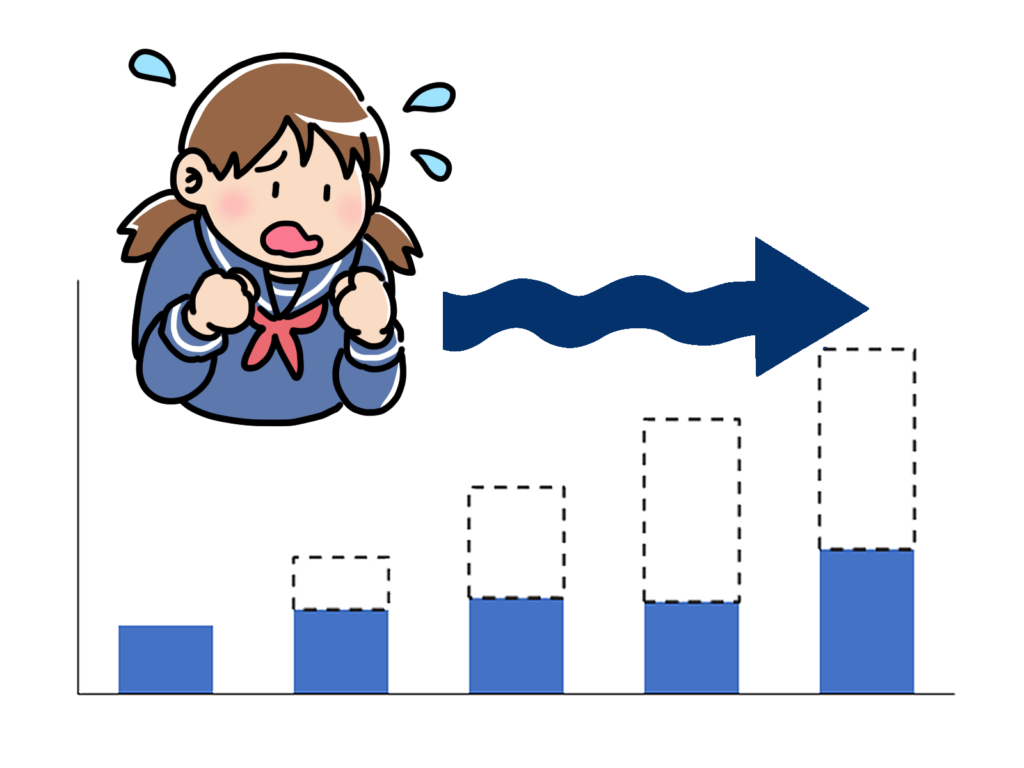
では、真の学力向上、本質的な理解のためには、どうすればよいのでしょうか?
答えは明確です。「ミスを消さずに、自分のしてしまったミスを把握すること」が重要なのです。
単純な計算ミスであっても、九九のうろ覚えが原因なのか、約分ミスなのか、符号のミスなのか、四則計算のミスなのか、その原因は様々です。小学校低学年では、答えにたどり着くまでの手順は比較的少ないですが、高学年や中学生になると、複数の手順を経て答えにたどり着くため、どの段階でミスをしたのかを特定することが非常に重要になってきます。
この「ミスの発見」こそが、学力向上の重要な要素となるのです。
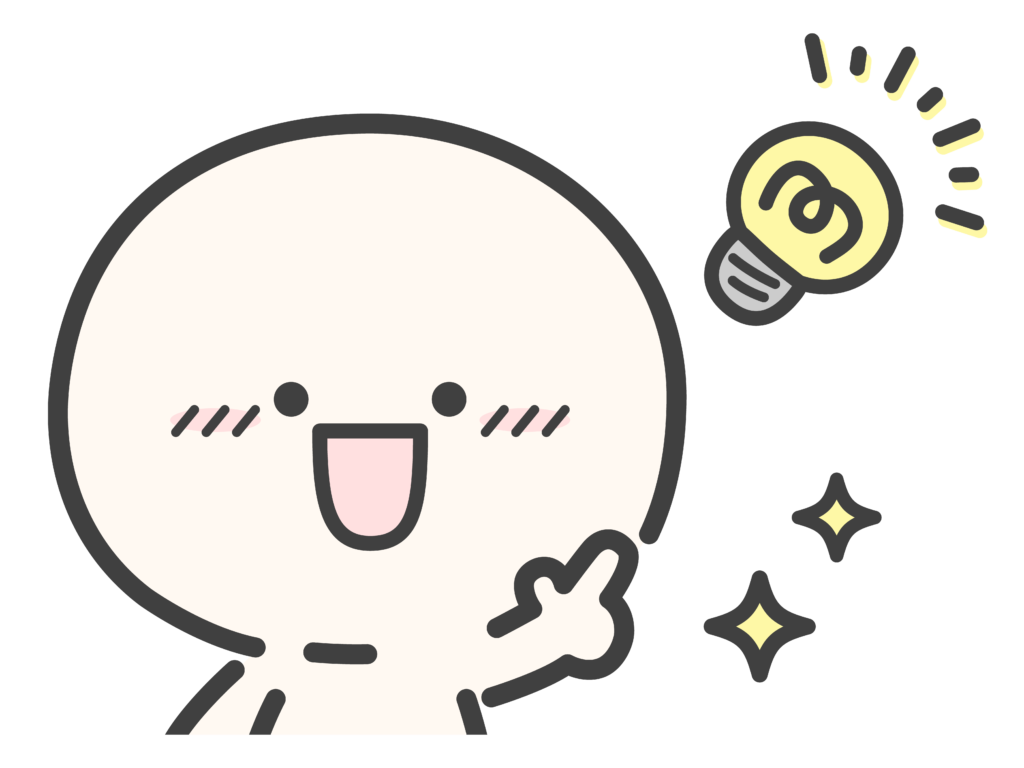
2025年現在、AIを活用した学習教材では、ミスした問題の類題を提示することはできますが、個々の生徒がどのようなミスをしたのかを分析し、理解させることまではできていません。「ミスしたから全部消して、解きなおす」という従来型のアプローチでは、ミスを発見して修正する機会を逃してしまい、学習効果は限定的なものとなってしまいます(ただし、近い将来、子どもたちがタブレットに途中の計算過程を記入することで、AIがそれを分析し、ミスの箇所を特定できるようになるかもしれません。Wordで文法ミスを青線や赤線で指摘してくれるように、数式でもミスの種類を判定してくれる時代が来るでしょう。おそらく2~30年後には実現するのではないでしょうか)。
ミスをした時、すべてを消してしまうのではなく、自分がどのようなミスをしたのか、なぜそのミスをしてしまったのかまで理解できれば、同じミスを繰り返す可能性は大きく減少します。人には誰しもクセがあり、よく起こすケアレスミスの傾向があるものです。その傾向を把握できている生徒とそうでない生徒では、重要なテストでの実力発揮に大きな差が出てくることは明らかです。
私たちLEAFでは、生徒一人ひとりのミスを丁寧に分析し、そのミスを克服するための最適な指導方法を見出すことに力を入れています。単なるミスなのか、根本的な理解が不足しているのかによって、指導のアプローチは大きく変わってきます。単に解きなおして正解を出せるようになるだけでは不十分です。ミスをした過程を理解し、正解に至るまでの修正点を明確に把握することで、安定した得点力が身につき、それが自信にもつながっていくのです。
実は、正解できた時よりも、ミスをした時の方が学べることは多いはずなのです。しかし、多くの塾や教師は、解きなおして正解できればそれでよしとしがちです。ミスこそが成長のチャンスととらえ、それを活かした指導ができる教育機関が増えていくことを、心から願っています。
【LEAFの体験授業・お問合せは】
・体験授業・ご入会・ご退会 ~2025年度入会予約受付中~
・お問い合せ
【学力支援ページもご覧ください】
・【脳葉強化 ~ひらめきラボ~】 脳細胞フル回転!問題解決への挑戦!
・ 頑張る子のために~反復プリント~【ダウンロードページ】