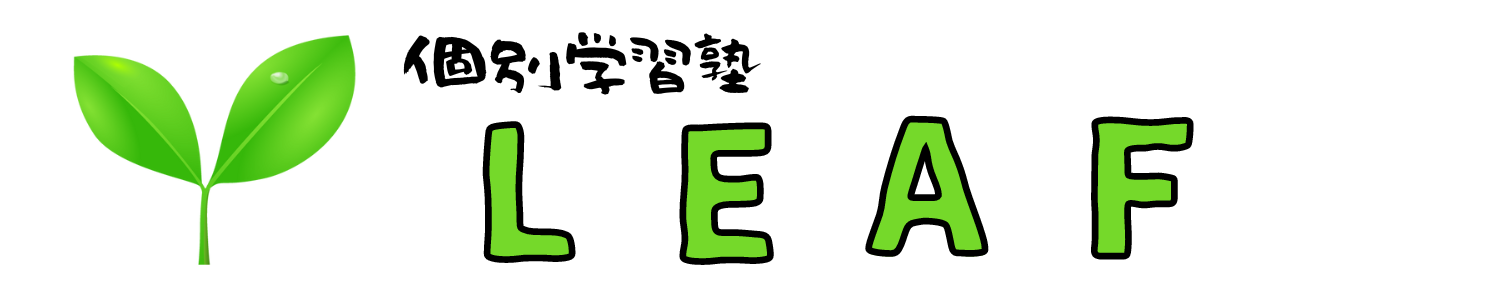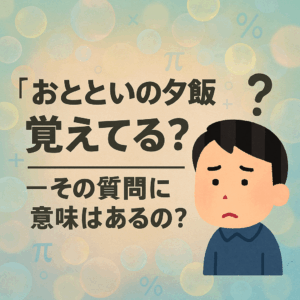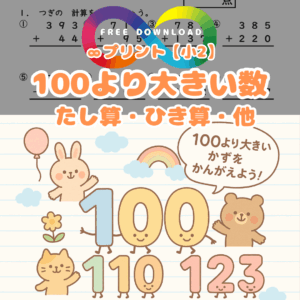【脳葉強化】『ルールを利用できる人・される人』 ひらめきラボ《0024》 ~ルールは守るものではなく、理解して使いこなすもの~
解答:
下の解説をご覧ください。
解説
A国通貨、B国通貨という表現にしますね。
A国では、「B国通貨の1万円=A国通貨9,000円」、
B国では、「A国通貨の1万円=B国通貨9,000円」ということです。
自分がA国にいたとします。
まず、A国通貨9,000円で、B国通貨1万円をゲットします。
次にB国に移動し、B国通貨1万円のうち9,000円を使って、A国通貨1万円をゲットします。(B国通貨1,000円残ってますね)
この時点で、A国通貨9,000円を使って、B国通貨1,000円とA国通貨1万円となりましたね。
つまり、A国通貨で1,000円のプラスです。
金額を大きくしたり、この往復を何度も使うだけで、大金持ちになれますね!
要するに、国を移動する前に相手国の通貨に換金してから移動すると、どんどんお金を増やすことができますね。
逆に、相手国に行ってから換金してしまうと、どんどん資産は減ってしまいます。
このことに気が付けるかどうかで得するか、損するか変わってきますね。
(実際は、こんなことが起きないような仕組みになっているので、現実的ではありませんね)
でもルールをうまく利用して得している人が世の中にいるんですよね~
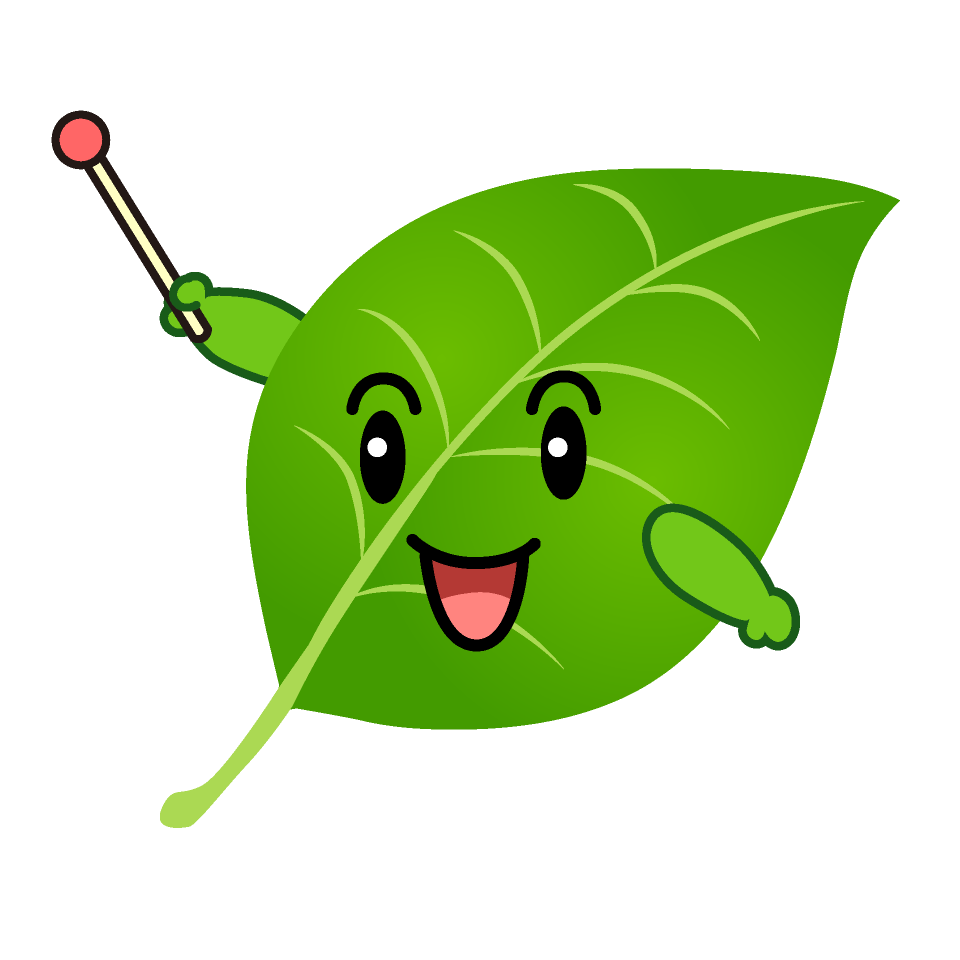
いかがでしたか。損をしない生き方ができそうですか?
ちなみに、AIたちにも同じ問題を解いてもらいました。
2025年4月下旬時点で、今回の問題をAIにも解いてもらいました。
ChatGPTは、1回目の回答では正確に答えられず、聞きなおしたところ、2回目の回答で正解を得られました。
Claudeは、同様に、1回目では損する方法しか答えられず、聞きなおしたところ、2回目の回答も正解にはたどり着きませんでした。
代わりに、為替レートを利用した商売を考えてくれました。
Geminiは、1回目の回答で正解しました。
Geminiの回答
A国でB国の1万円を9,000円で手に入れます。
次に、その手に入れたB国の1万円をB国に持ち込みます。
すると、B国ではA国の1万円が9,000円の価値になるので、彼はそのB国の1万円を9,000円の価値としてA国のお金に両替してもらうのです。
つまり、彼は実際には価値が変わっていないB国の1万円を、A国とB国の間で両替することで、差額の1,000円を手に入れたと考えられます。
ただし、これは手数料や両替レートの変動がないという、かなり単純化した考え方です。実際には、両替の際に手数料がかかったり、両替レートが常に一定とは限らないため、必ずしも儲けが出るとは限りません。
それでも、この状況をいち早く理解して行動すれば、一時的に利益を得るチャンスはあったかもしれませんね!
「ルールを利用できる人・利用される人」~子どもたちに伝えたい視点~
私たち教育者は、日々子どもたちと接する中で、ルールの意義や在り方について考える機会が多くあります。学校生活には校則や学級のルールがあり、学習にも時間割や課題提出などの決まりごとがつきものです。
そのルールに対して、子どもたちの受け止め方は実に様々です。「面倒くさい」「なんでこんなことを守らなきゃいけないの?」という反発の声もあれば、「決まりだから仕方ない」と黙々と従う子もいます。
しかし、ルールの捉え方によって、子どもたちの成長や学びの質が大きく変わることがあります。
あるとき、授業中の自主学習で、スマートフォンの使用をめぐってこんなことがありました。「スマホは禁止」と明記されたルールに対し、ある生徒が「この英単語アプリは許可されますか?」と尋ねてきたのです。ルールの趣旨を理解し、学習目的に沿った使い方を提案する姿勢には感心させられました。
これはまさに、ルールをただ守るのではなく、“活かす”という行動です。自分の目的や状況に応じて、ルールの中で最大限の力を発揮しようとする姿勢は、学びに対する主体性の表れでもあります。
一方で、別の生徒は同じルールに対して、「どうせダメなんでしょ」と最初から諦めてしまっていました。こうした子どもたちは、ルールによって自分の行動が狭められていると感じ、受け身の姿勢に陥りがちです。
ここで私たち教育者に求められるのは、単にルールを守らせる指導ではありません。ルールの背景や目的を丁寧に伝え、その中でどう自分らしく動けるかを子どもたちに考えさせることです。ルールを“壁”ではなく“道具”として見せる工夫が、子どもたちの主体的な成長につながります。
また、スポーツやゲームでもルールの使い方が子どもたちの力を伸ばします。たとえば将棋には、駒の動かし方という厳格なルールがあります。しかし、そのルールの中で創意工夫を凝らし、時にはあえて駒を犠牲にしてでも全体を有利に進める――こうした発想力は、ルールを理解し、使いこなす力そのものです。
このような視点を育てていくことが、これからの社会を生きる子どもたちにとって、非常に大切だと感じます。
ルールをただ「我慢するもの」ととらえていると、常に不満やストレスに悩まされることになります。けれど、ルールの意味を理解し、その中で自分がどう動けるかを考えられるようになると、ルールは強力な「味方」になるのです。
社会に出ても、常にルールと向き合っていくことになります。税金、契約、交通法規…。そうしたルールを「利用される」側にいるのか、「利用する」側に回るのかで、人生の自由度は大きく変わってきます。
「ルールは守るものではなく、理解して使いこなすもの」
もちろん、ルール違反を勧めるわけではありません。ただ、ルールをただの「壁」と思うのではなく、「道具」として見てみる。そんな視点を持つだけで、子どもたちの目に映る世界ががらっと変わるかもしれません。